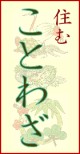●告朔のき羊
読み(ひらがな)こくさくの きよう。 |
意味古いしきたりなどが、ただ形式だけになっていることのたとえ。 |
解説古くから伝わる習慣や行事などは、しっかり考えもしないで簡単に廃止してはいけない、ということのたとえのようです。 昔、古代中国で暦を発布する時に行った儀式のことを「告朔」といい、その儀式の時にいけにえとして祖先の霊前に お供えした羊のことを「きよう」と言っていたようです。孔子が生きていた頃、この「告朔」はすでに行われず、いけにえの 羊だけを形式的に祖先の霊前にお供えしていたようで、当時の国の偉い人が、「きよう」も廃止しようとしたら、 孔子が儀式がすたれるのを恐れ、きようの廃止に反対したということが由来のようです。 |
重要語の意味告朔=「こくさく」と読み、古代中国で12月に天子より来年の暦を受け、それを祖先の霊前に納め、 暦の年の毎月ついたちの日にいけにえとして羊を供え、その暦を発布した儀式。 き羊=「きよう」と読み、告朔に供える、いけにえの羊。 「き」は、正式には と書く。
しきたり=昔から続いている習慣など。
朔=「さく」と読み、月が新月になる日。ついたち。 と書く。
しきたり=昔から続いている習慣など。
朔=「さく」と読み、月が新月になる日。ついたち。
 =「き」と読み、いけにえ。
いけにえ=国や子孫の繁栄を願い、また感謝の意を込め生き物を供えること。
ついたち=月の第一日。
暦=「こよみ」と読み、1年間の月と日を定めたもの。カレンダー。
発布=「はっぷ」と読み、広く知らせること。
祖先=「そせん」と読み、父母以前に続いてきたいのち。
霊前=「れいぜん」と読み、祖先をおまつりした所の前。
廃止=「はいし」と読み、行事などをやめること。 =「き」と読み、いけにえ。
いけにえ=国や子孫の繁栄を願い、また感謝の意を込め生き物を供えること。
ついたち=月の第一日。
暦=「こよみ」と読み、1年間の月と日を定めたもの。カレンダー。
発布=「はっぷ」と読み、広く知らせること。
祖先=「そせん」と読み、父母以前に続いてきたいのち。
霊前=「れいぜん」と読み、祖先をおまつりした所の前。
廃止=「はいし」と読み、行事などをやめること。
|
いわれ(歴史)と重要度論語・はちいつ篇17。 重要度=☆☆☆ |
スポンサードリンク